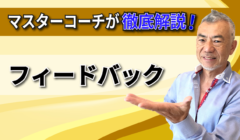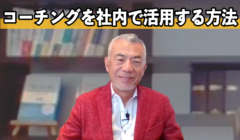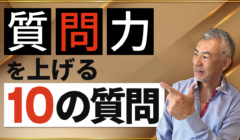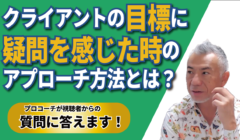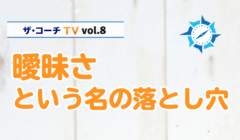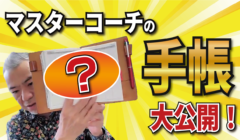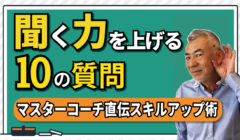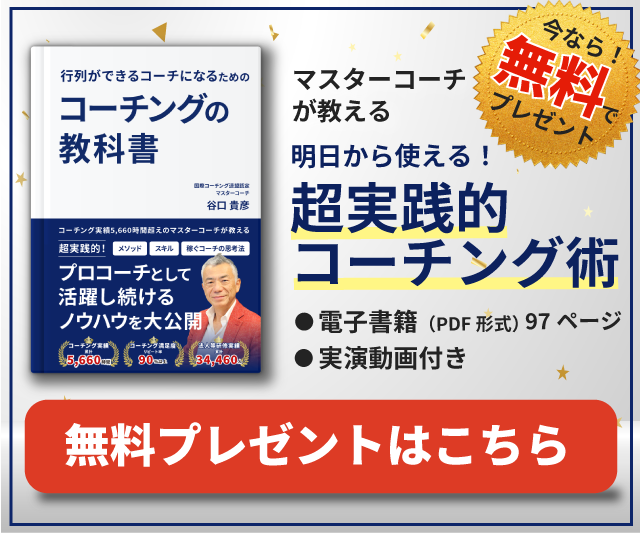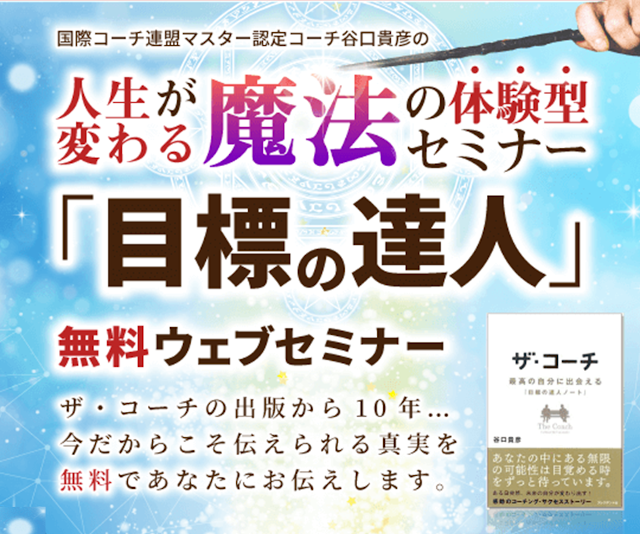クライアントに共感は不要?- アクティブリスニングの極意とは? #131
―― 今回は「共感とは?そして、クライアントに本当に共感する必要はあるのか?」というテーマで谷口コーチにお話を伺っていきたいと思います。
コーチングについて、いろんな方がそれぞれの視点で「コーチングには○○が必要だよ」とおっしゃっているのを目にします。もちろん、何が正しくて、何が間違っているとか、そういった考えではないのですが、谷口コーチの下で、6年以上にわたって「門前の小僧」としてお話を聞き続けていると、「ん?これは言葉の定義が曖昧だな?」とか、「言葉の意味と実状は違うのではないか?」と感じることが度々あるんですね。
そして、この「言葉の定義」を明確にすることの重要性も谷口コーチの下で学んできたのですが、今日、谷口コーチに聞いてみたい言葉が今日のテーマの「共感」という言葉なんですね。著名な方を含め、色んなコーチたちが、「コーチングには「共感」が重要だ」とおっしゃっています。ですが、この「共感」という言葉を辞書で調べてみると、
“共感とは?” 感情や心理的状態、あるいは人の主張などを、自分も全く同じように感じたり理解すること。同感。
と書かれていたんです。この「共感」を、辞書に書かれているとおりの定義から考えると、『コーチングには「共感」が重要だ。』ということにものすごく違和感を覚えたんですね。
そして、谷口コーチがアクティブリスニングについて教えられているときに、共感が重要だとは一切、言われていなかったなぁと思ったんです。
谷口:多分コーチ人生で一度も言ってない。
―― 売れっ子コーチになると、数十人のクライアントにコーチングを提供することになると思いますが、全員のクライアントの感情や心理状態、あるいは主張をすべてを自分も全く同じように感じたり、理解していると、コーチは心理的な負担が大きすぎて、それをやっちゃうと死んじゃうんじゃないかと思うんですね。
谷口:僕ありましたよ。あのね、巻き込まれる感じ。同じように感じちゃうと、苦しくなっちゃう、辛くなっちゃうし、すごく狭くなっちゃうし。一時コーチング苦しいなと思う時期ありました。その時から、これちょっと違うなと思った、若松さんの言った通りだと思います。
―― そこから考えると、もしかすると、コーチングには「共感」が重要ではなくて、「共感していると相手に感じてもらうこと」が重要で、コーチは実際には共感する必要はないのではないかと感じたんですね。
プロコーチやコーチングを提供されている方の中には、もしかすると、この「共感」という部分で疲弊していたり、悩まれている方もいらっしゃるかもしれないと思いまして、谷口コーチから、コーチングにおける「共感」の定義について、教えていただきたいと思いました。谷口コーチいかがでしょうか。
コーチングにおける「共感」の定義とは?
谷口:ほんと、ちょっとした言葉の違いなんですけど、ICF(国際コーチング連盟)のコアコンピテンシーで行動規範には、『クライアントの考え、主張、感情や、気持ちに共感や関心を示す』って書いてある。「共感する」とは書いてないんですよ。
共感する、しない、ではなくて、共感を示すか、示さないか。で、コンピテンシーには共感を示しましょうって書いてある。
共感すると共感を示すって違わない?
―― 違います。
谷口:ですよね。共感するは、若松さんが言った通り、共感の意味です。同じように感じて、同じように辛い気持ちや楽しい気持ちになったり、「同じ考えだ」っていうふうに自分も同感する、同意する。
ってことはさ、クライアントがいっぱいいたら、こっちの人は苦しいかったら、やっぱ苦しい、こっちの人はAって言ったら「Aですね。」でも、こっちの人がBって言ったら「Bですね」って言って、ぐちゃぐちゃになっちゃう。
でも、共感を示すっていうと、「あ、辛いんだね。」、「そう考えてるんだね。」、「Aっていうふうに考えてるんだね。」ていうのは示してるけど、共感はしてないんです。
だから、この違いが区別できるといいね。共感するではなくて、共感を示すていうことなの。
僕はすごくやっぱりコーチングやってきて面白いなっていうのは、一字違うだけで全然意味が違っちゃうんですよ、ちょっと違うだけで。
これ、名詞、助詞、動詞の組み合わせだったりすると、僕たちはコミュニケーションの専門家であるわけですね。
ってことは、この一字違うだけで全く違う伝わり方をするっていうことに、非常にこう配慮をする必要があるんだろうなって。
それぐらいやっぱりプロ意識を持って僕はやった方がいいので、共感するではなくて、共感を示すは重要だと。
じゃあ、なぜか?ということですね。
共感を示す重要性~親密と信頼の区別~
谷口:ICF(国際コーチング連盟)では、関係性のことを『親密で信頼が構築されている関係性』をいっているんですね。
これ、別物なんですよ、親密と信頼。
「親密」って、何でも話せるような心を許せる関係。
「信頼」っていうのは、お互いのプロジェクトやお互いの成長のためにお互いを信じて頼り合う関係。だから、非常にこう、人間的な部分と、非常にビジネス的な感じがするんですよね。
特にこの人間関係として、お互い「もう、若松さんなら何でも話せるわ、心許せるし、こんな話も聞いて、おかげでスッキリできたわ。」とかっていうのは親密。
「それについて僕はAなんだけど。」「いや、それについて僕はBだと思う。」「それぞれ同じように2人の考えをちょっともう一度考えてみよう、それで、2人にとってベストな考えを導き出そうよ。」っていうのは、お互いの主張を尊重してますよね。
この2つを同時にやってるんですよ、プロコーチは。
それで、その共感を示すってのは、「あ、若松さんはAという考えなのね、で、僕はBだった。」っていうのは、相手の主張に関心を示してるわけです。もっと言ったら、尊重してるわけです、否定してないですよね。
なので、こういうことを共感を示すっていってるんだと。
だから、同じように感じたり、同じように考えたりするではなくて、相手の感情とか感じてることに関心を示す。で、相手の考えてることや感情、主張に関心を示す。それはとっても重要だと。
で、その量が多いか少ないかで、その関係性、親密で、信頼関係の絆の太さは変わると思う。
なので、共感はせんと。僕は。
「共感する」と「共感を示す」クライアントへの声かけの違い
谷口:頭の中で想像してほしいんだけど、クライアントさんはやっぱり当事者なんで、いろんなことに当たるわけですよ。チャレンジしたり、失敗したり、悩んだりするんですね。
イメージはね、ずっとこう、平坦な道を歩いてたのが、時々、谷底に落ちてるみたいな感じ。
それを前は、僕が一緒に下まで降りていって「大丈夫?」って言ってたの。そうすると、巻き込まれちゃう。これは共感しちゃってるんですよ。それで、僕が苦しくなっちゃう。
ではなくて、やっぱトップコーチたちって、ある意味すごく客観的なんです、巻き込まれてないですよね。
で、イメージ絵がね、こんな感じだったんです。
クライアントさんが「失敗したー、ダメだった―。」とかって言って、どんどん、谷底に落ちて、もうこれ以上底は無いって位までに落ちてるのに、上の方から「おーい!」って声かけてる。
上の方で、「待ってるからねー。」って言って、声かけてる感じなんですね。
これができるようになってから、やっぱり月に20人とかっていうクライアントさんのコーチ。
ただ、共感を示すことはすっごく訓練します。
例えば、辛い時、「辛いね。」っていうのと、「辛かったね、しんどかったね。」ていうので、「しんどいね。」っていう時と、「しんどかったね。」とか「しんどそうだね。」っていう時って、ちょっと違いそうじゃない?
―― 違います。
谷口:これ、1文字ぐらいしか違わないですよ。ってことは、前者を日常会話でよく言うんですよ。
でも、後者のたった1文字。例えば、「頑張ってね。」っていう時と、「頑張ったね。」とか、「頑張ってるね。」っていうので違わない?届き方って。
―― 違います。
谷口:だから、何にも考えないで共感してる時に発してるコミュニケーションの言葉と、共感を示すっていうのはどういう言い方なんだっていうのはすごく考えて練習します。
でも、みんなわかってるみたいよ、僕は共感してないっていうのは。(笑)
だから、めっちゃ共感を示してくれてるので、相手は共感してもらってるっていう風に感じるみたいね。
なので、考えや感情や主張は、コーチは尊重する。で、それをすごく配慮する、考慮する、だけど、共感はせん、というようなスタンスなんじゃないかなと思います。
プロコーチに大事なスタンスとは?
谷口:あと、コアコンピテンシーにこういうこと書いてあるんですね。
『コーチは自分の感情を整える能力を開発し、維持している。』ってことは、コーチは感情が安定してるってことです。ってことは振れないってことですね。
そういう風に共感したら振れるってことじゃない?苦しい、楽しいっていうのに。
じゃなくて、クライアントがどう振れても、コーチは自分の感情は安定してる。ただし関心は示す。
こういうスタンスをずっと持ち続けるのがプロコーチだと思います。
だから、僕は、「プロコーチは共感せん!」と言って、ただめっちゃめちゃ共感は示す。
で、その共感してる時に発してしまう言葉と、共感を示すときに伝える言葉の区別や、どういうセリフがそれに当たるんだろう、というようなツール、言葉を整えたり、その練習はすごくします。
なので、若松さん、すごくいいとこついたと僕は思う。
―― ありがとうございます。
谷口:僕の場合で言うと、共感はしない。共感はめっちゃ示す。
で、関係性親密で信頼関係を高く築き続けて、最高のパートナーシップを築く。というスタンスを維持しようと。
共感を活用したビジネス・マーケット
谷口:ただし、最近さ、共感ビジネスとか共感マーケットっていうよね。あれは結局、何かをただ客観的に説明するより、心が同じように感じたり、心が動いた方が物が売れたり、人が動くってことでしょ?
だから、昔で言うと商品売りたかったら商品のスペックだとか、性能だとか、エビデンスを話してましたよね?
でも、それでは売れなくなったので、この商品が生活の中にある物語をCMとかで流すわけでしょ。
「俺それだー。」とか思うから買うってことですね、スペックでは買わないってことですよ。その商品を持つことで得られる感情を買うんですね。
なので、ビジネスとかマーケティングでは共感した方がいい。
―― 共感を上手く活用する。
谷口:その方がうまくいくと思う。
だから、コーチングするときは共感をしない、共感を示すけど。
自分を売る時にとか、セールスやマーケティングの時には、逆にユーザーの共感を生み出すようなこと。だから、そこはストーリーだとか体験談とかになってくるのかなって思います。
―― 改めて、この1文字の違いの重要さ、勉強になりました。ありがとうございます。